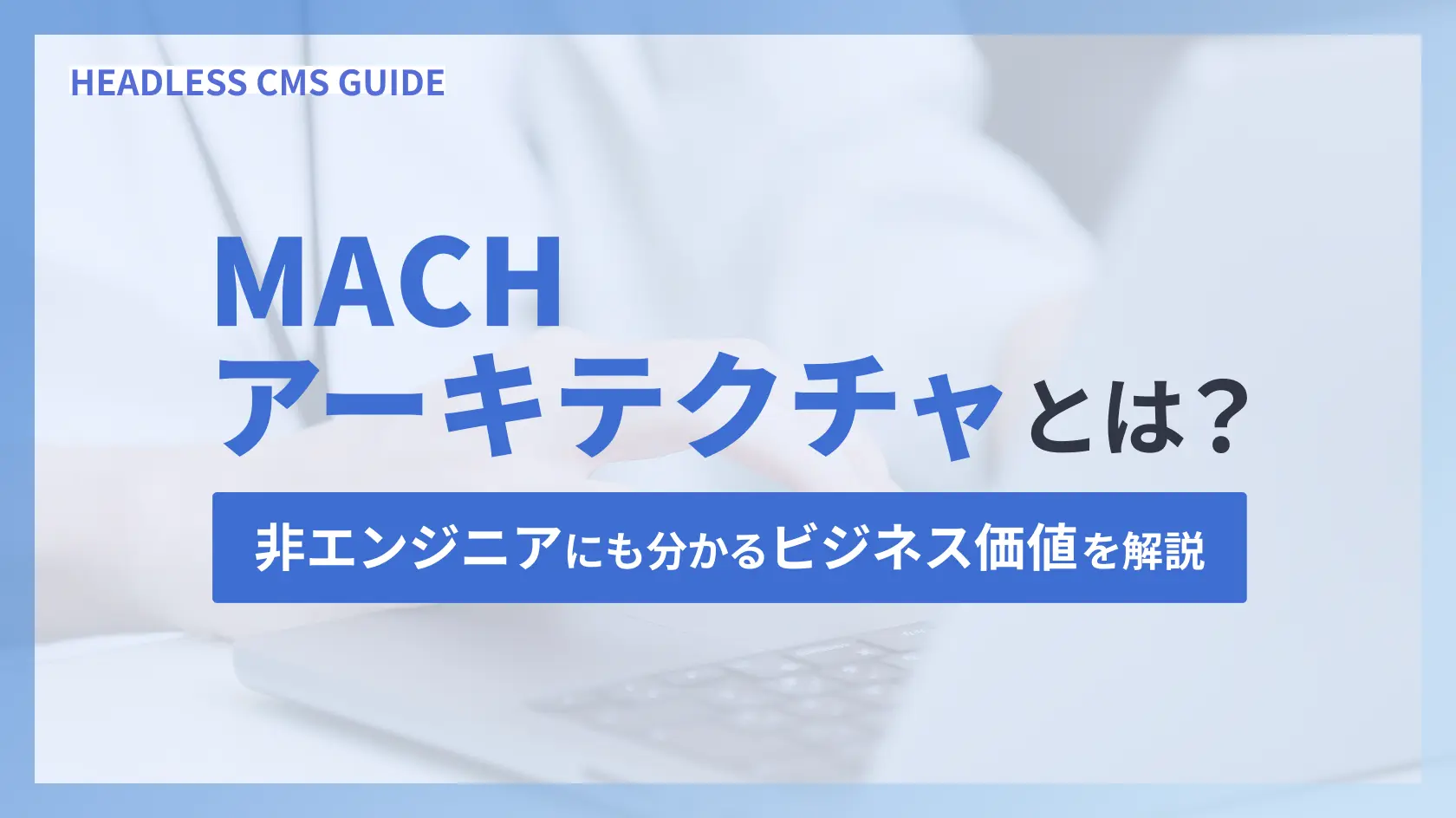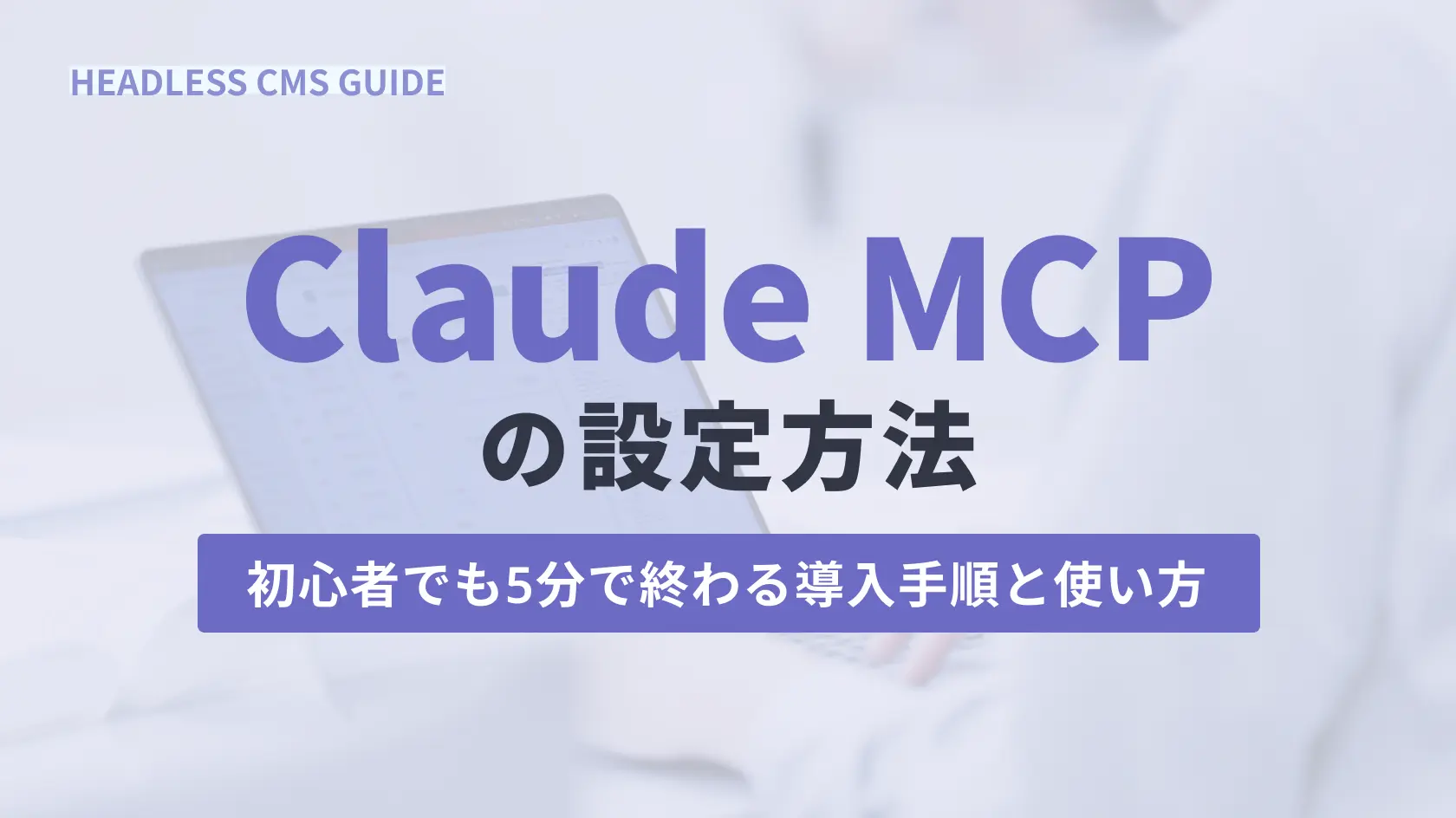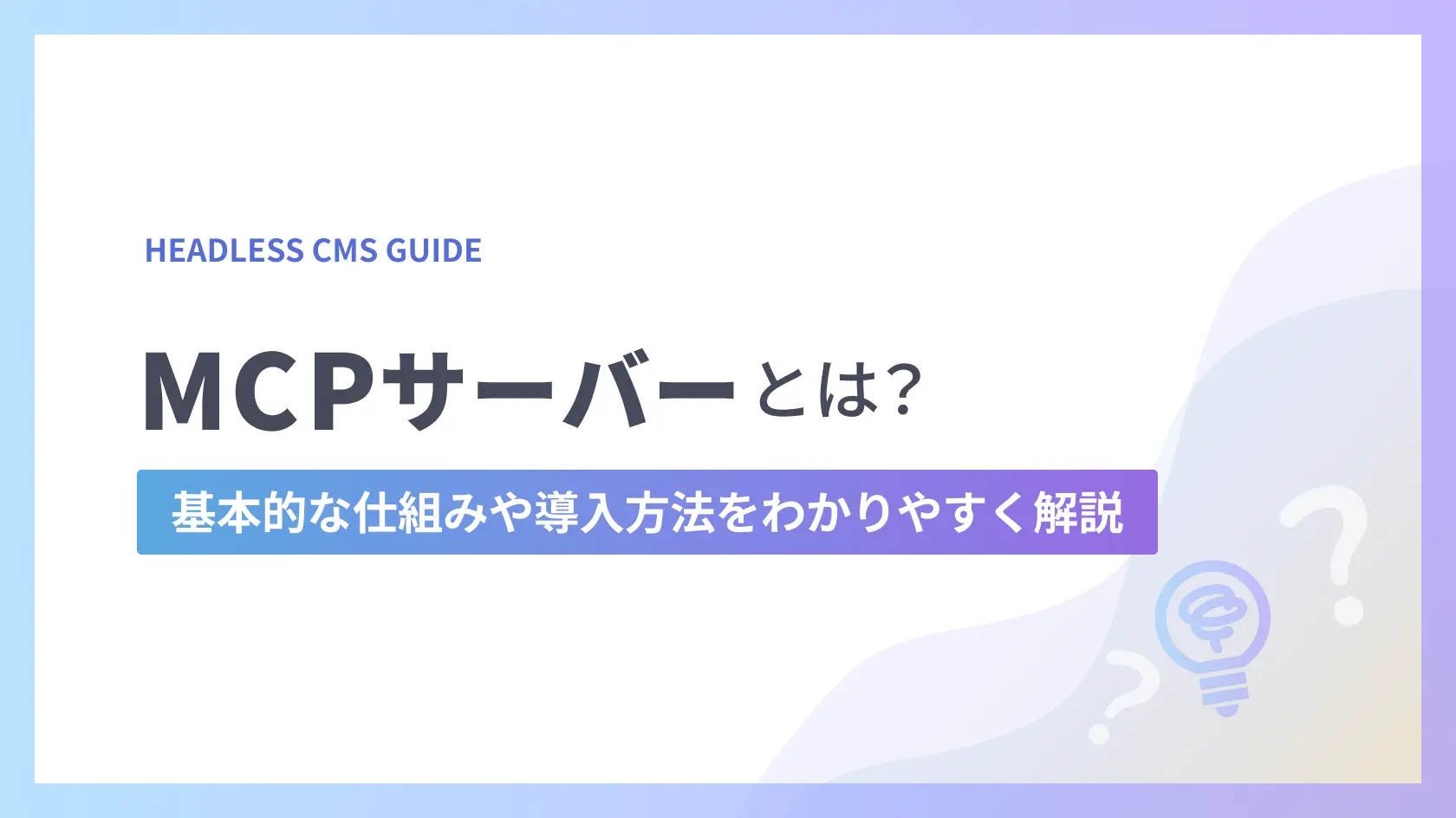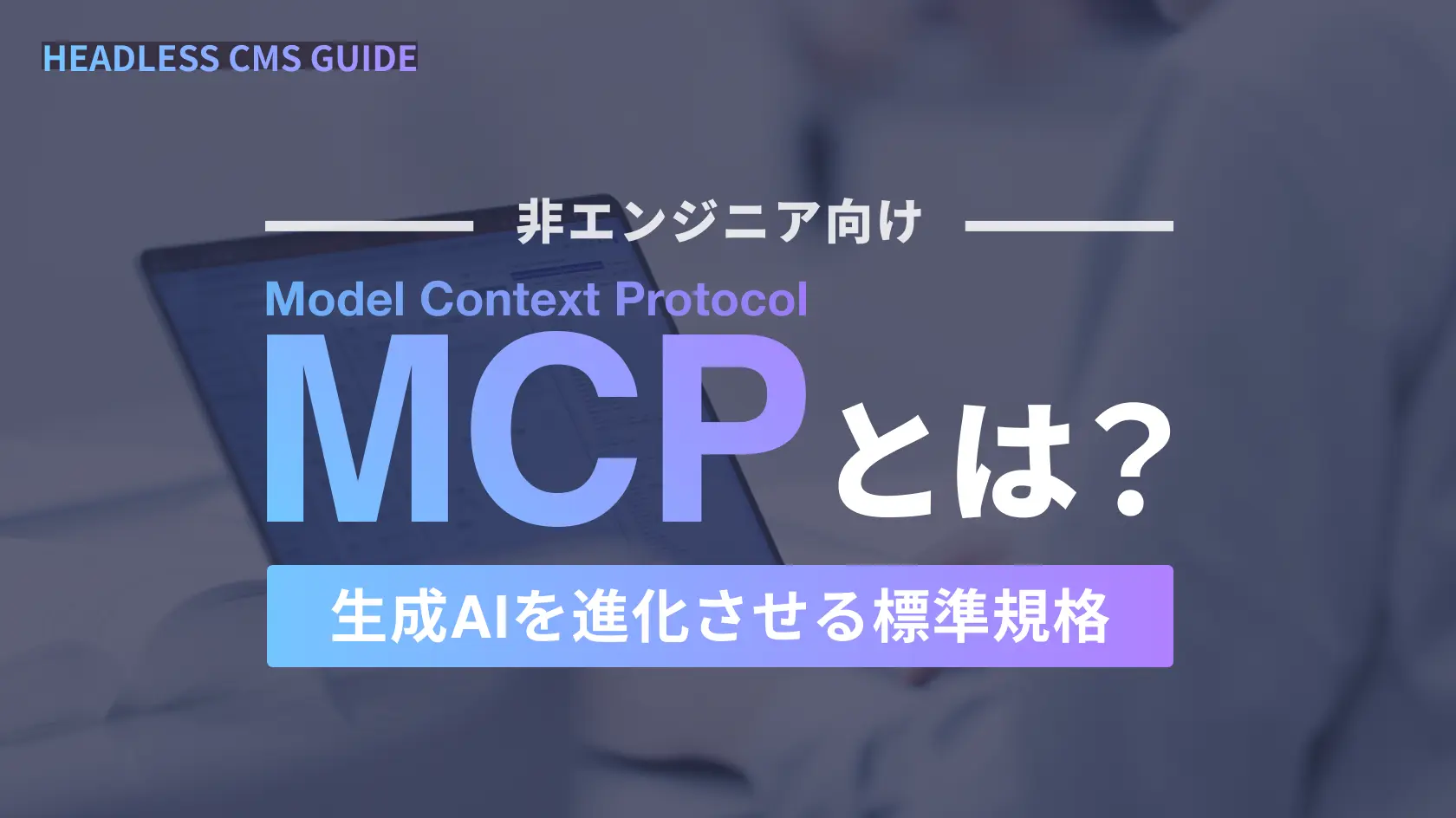目次
MACHとは
MACHアーキテクチャとは、特定の製品名ではなく、ビジネスの要求に応じて機能を自由に組み合わせ、変化に強いシステムを構築するための設計思想です。
この名前は、4つの技術原則の頭文字から構成されています。
ここでは、それぞれの原則をブロックを組み立てるイメージに例えながら、非エンジニアの方にも分かりやすく解説します。
M - Microservices(マイクロサービス):機能ごとの小さな専門チーム
マイクロサービスとは、システム全体を「決済」「在庫管理」「会員情報」といった、機能ごとの独立した小さなサービス(ブロック)の集合体として捉える考え方です。
従来のシステムが、全ての機能を持つ巨大な一つの塊だとすれば、マイクロサービスは目的別に分かれた小さなブロックの集まりです。
各ブロックは独立しているため、例えば「決済ブロック」だけを新しいものに交換したり、修正したりすることが、他のブロックに影響を与えることなく可能です。
これにより、機能ごとの開発や改善が、迅速かつ安全に行えるようになります。
A - API-first(APIファースト):機能同士をつなぐ「通訳」
APIとは、異なるサービス(ブロック)同士が情報をやり取りするための「接続部分の規格」や「通訳」のようなものです。
APIファーストとは、全ての機能を、まずAPIとして外部から利用できる形で設計する考え方を指します。
各ブロックが共通の規格(API)で会話できるようにしておくことで、ブロック同士の連携がスムーズになります。
例えば、「会員情報ブロック」が提供するAPIを使えば、「決済ブロック」や「ポイント管理ブロック」が顧客情報を簡単に参照できるようになり、柔軟なサービス連携が実現します。
C - Cloud-native(クラウドネイティブ):いつでも拡張できる「土地」
クラウドネイティブとは、システムの土台として、クラウドサービスの利用を前提とする考え方です。
クラウドは、必要に応じて広さを自由に変えられる魔法のような土地に例えられます。キャンペーンでアクセスが急増した際には、自動的に土地を広げて(スケールアウトして)安定稼働を維持し、アクセスが落ち着けば元の広さに戻すことができます。
このようなクラウドの持つ伸縮自在な能力を最大限に活用することで、常に最適なコストで、安定したサービスを提供し続けられます。
H - Headless(ヘッドレス):見た目を自由に着せ替え
ヘッドレスとは、ユーザーの目に触れる部分(フロントエンド=見た目)と、ビジネスロジックを処理する部分(バックエンド=機能)を完全に分離する考え方です。
ブロックで組み立てた本体(機能)はそのままに、目的に合わせて外側の見た目だけを自由に着せ替えられるイメージです。
これにより、同じ機能(例えば商品情報)を、Webサイト、スマートフォンアプリ、店舗のデジタルサイネージなど、様々なチャネルに対して最適化して提供できます。
結果として、顧客はどのチャネルを利用しても、一貫性のある優れたブランド体験を得られます。
MACHアーキテクチャが注目される背景
MACHアーキテクチャが注目を集める背景には、多くの企業が利用してきた従来のITシステム、通称「モノリシック(一枚岩)」アーキテクチャが抱える構造的な課題があります。
モノリシックとは、EC機能、コンテンツ管理、在庫管理、顧客管理といった、あらゆる機能が一つのかたまりとして密接に結びついて構築されたシステムです。
オールインワンで便利な反面、この一枚岩の構造が、現代のビジネス環境において大きな足かせとなっています。
例えば、市場や顧客のニーズが目まぐるしく変化する中で、決済方法の追加など、一部の機能を少し変更したいだけでも、システム全体に影響が及ぶため、大規模な改修が必要になりがちです。
結果として開発に多くの時間とコストがかかり、ビジネスのスピード感についていけなくなります。
また、特定のベンダーが提供するパッケージに全ての機能を依存しているため、その提供範囲を超えるような、独自の新しい顧客体験を創造することも困難でした。
MACHアーキテクチャは、この「一枚岩」の構造を根本から見直すことで、これらの課題を解決する新しいアプローチとして期待されています。
MACHがもたらす3つのビジネス価値
では、MACHアーキテクチャを採用することは、マーケターや事業責任者といったビジネスサイドの担当者にとって、具体的にどのような価値をもたらすのでしょうか。
ここでは、特に重要な3つのビジネス価値に焦点を当てて解説します。
価値1:市場の変化に素早く対応できる「俊敏性」
MACHアーキテクチャがもたらす最大の価値は、ビジネスの「俊敏性(アジリティ)」の向上です。顧客ニーズや市場トレンドの変化に対し、迅速に行動を起こせるようになります。
新しい機能を数ヶ月ではなく数週間で試せる
従来のモノリシックなシステムでは、新しい機能の追加に数ヶ月単位の時間がかかることも珍しくありませんでした。
しかし、MACHアーキテクチャでは、各機能が独立したマイクロサービスとして存在するため、新しい機能のサービス(ブロック)を追加するだけで済みます。
例えば、新しいSNSと連携したログイン機能を試したい場合、その機能を持つサービスをAPIで連携させるだけで、迅速に市場に投入し、顧客の反応を見ることができます。
この試行錯誤のサイクルの速さが、競争優位性を生み出します。
キャンペーン毎に最適なツールを組み合わせる
期間限定のキャンペーンや、特定のターゲット層に向けたプロモーションを実施する際、その目的に特化した最適なツール(例えば、特定のクーポン管理サービスや、ライブコマースツールなど)を柔軟に組み合わせることができます。
キャンペーンが終了すれば、そのツールとの連携を解除するだけで済み、システム全体に影響はありません。
これにより、常に最高のツールセットで、効果的なマーケティング施策を展開できます。
価値2:自由に顧客体験をデザインできる「柔軟性」
顧客の期待値が上がり続ける現代において、優れた顧客体験(CX)の提供はビジネスの成功に不可欠です。
MACHアーキテクチャは、そのための柔軟な基盤を提供します。
Web、アプリ、店舗など、一貫した体験の提供
ヘッドレスの原則により、バックエンドのビジネスロジックは一つに集約されています。
そのため、Webサイト、スマートフォンアプリ、実店舗のPOSレジ、コールセンターの応対システムなど、顧客とのあらゆる接点(チャネル)で、同じ顧客情報や購買履歴、ポイント情報を共有できます。
これにより、顧客がどのチャネルを利用しても分断されることのない、一貫したシームレスな顧客体験を提供できます。
顧客データから最適なUIを追求
フロントエンドがバックエンドから完全に独立しているため、UI/UXの改善を迅速かつ継続的に行うことができます。
顧客の行動データを分析し、「このボタンの色を変えた方がクリックされやすい」「ここの表示順序を入れ替えた方が購入率が上がる」といった仮説を、バックエンドの制約を気にすることなく、すぐに試せます。
この高速なA/Bテストのサイクルが、コンバージョン率の最大化と、顧客満足度の向上に直結します。
価値3:将来の成長に備える「持続可能性」
ビジネスは常に成長し、変化し続けます。
MACHアーキテクチャは、長期的な視点でビジネスの成長を支える「持続可能性」を備えています。
特定のベンダーに縛られない技術選定
従来のオールインワンパッケージ型のシステムでは、一度導入すると、そのベンダーが提供する機能や技術に完全に依存してしまう「ベンダーロックイン」の状態に陥りがちでした。
しかし、MACHアーキテクチャでは、各機能を構成するコンポーネント(ブロック)を、それぞれの分野で最高の機能を持つ「ベストオブブリード」なツールから自由に選んで組み合わせることができます。
これにより、特定のベンダーに縛られることなく、常に自社にとって最適な技術を選び続けられます。
古くなった機能だけを交換・アップデート
5年後、10年後、現在最新の技術が陳腐化することは避けられません。
モノリシックなシステムでは、システム全体を大規模にリプレースする必要がありましたが、MACHアーキテクチャなら、古くなった機能(ブロック)だけを新しいものに交換するだけで済みます。
例えば、決済システムだけを新しいサービスに入れ替える、といった対応が可能です。これにより、常にシステム全体を最新の状態に保ち、長期的な技術的負債を抱えるリスクを低減できます。
MACHアーキテクチャ導入の課題
多くのビジネス価値をもたらすMACHアーキテクチャですが、導入は決して簡単ではありません。
成功のためには、導入前にMACHアーキテクチャの課題を理解しておくことが重要です。
複数のツールを管理するため複雑になる
MACHアーキテクチャは、様々な専門ツール(ブロック)を組み合わせて作られます。
それぞれのツールは非常に高機能ですが、それら全体を連携させ、一つのシステムとしてスムーズに動作させるための「オーケストレーション(指揮)」は複雑になりがちです。
どのデータがどのシステムを流れ、どこで処理されるのか、その全体像を管理し、問題発生時に原因を特定するには、高度な技術力と設計能力が求められます。
組織体制をかえる必要性がある
システムの構造が、機能ごとに独立したマイクロサービスの集合体に変わるのに伴い、開発チームの体制もそれに合わせて変革する必要があります。
機能ごとに専門の小規模チームを作り、各チームが自律的に開発・運用を行うといった、新しい開発文化の醸成が求められる場合があります。
また、ビジネス部門と開発部門が、これまで以上に密に連携し、どの機能をどのツールで実現するかを共に考えていく必要も出てきます。
初期投資と移行計画の難易度が高い
既存の巨大なモノリシックシステムから、MACHアーキテクチャへ一度に移行するのは、コストとリスクの観点から現実的ではありません。
多くの場合、まずは既存システムの一部(例えば、フロントエンドだけをヘッドレス化する、特定の機能だけをマイクロサービスとして切り出すなど)から段階的に移行を進めていくことになります。
どこから着手し、どのようなロードマップで進めていくのか、綿密な移行計画と、それを実行するための初期投資に関する経営層の理解が不可欠です。
まとめ|MACHは未来のビジネス基盤を支える新しい選択肢
本記事では、MACHアーキテクチャを、ビジネスの視点からその価値と課題について解説しました。
MACHは単なる技術的なワードではなく、変化の激しい時代において企業が競争力を維持し、成長し続けるための設計思想です。
MACHアーキテクチャの導入には、技術・組織・経営面での課題を伴いますが、その時々で最適な機能を柔軟に組み合わせ、常に最高の顧客体験を追求できる基盤を持つことは、これからのビジネスにおいて不可欠な要素となるでしょう。
まずは自社のビジネスが抱える課題を整理し、その解決策としてMACHが有効な選択肢となりうるか、検討を始めてみてはいかがでしょうか。