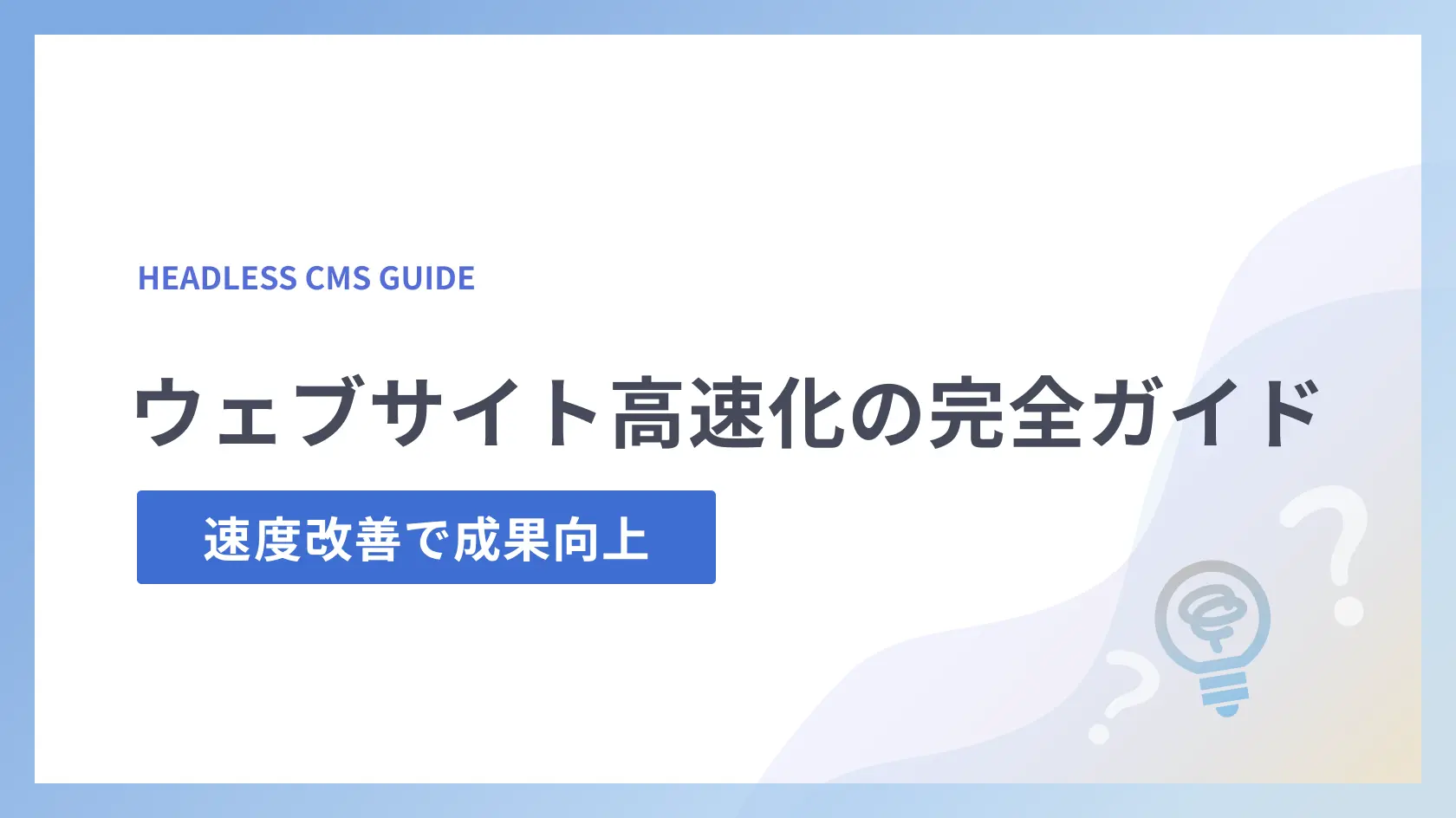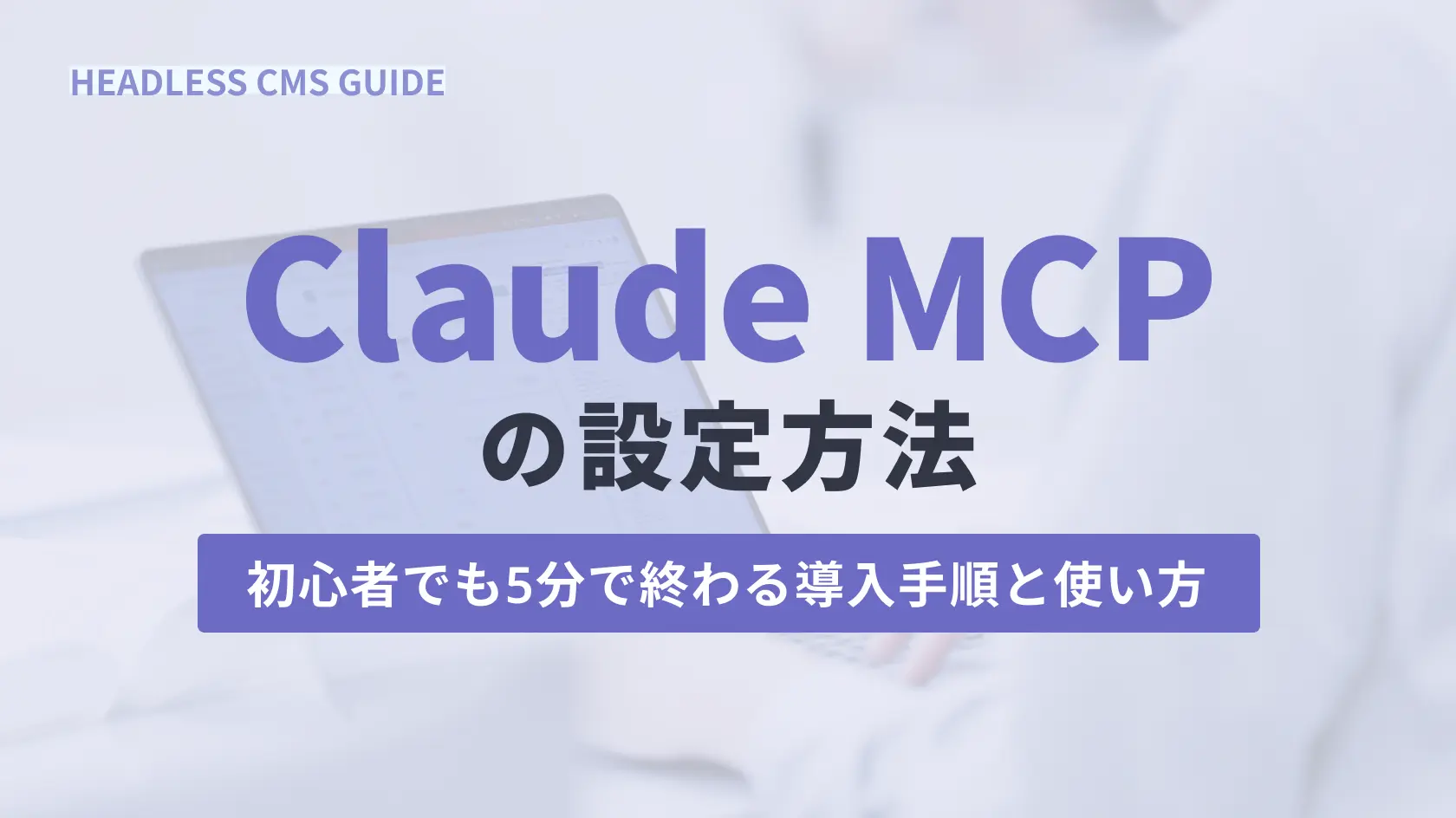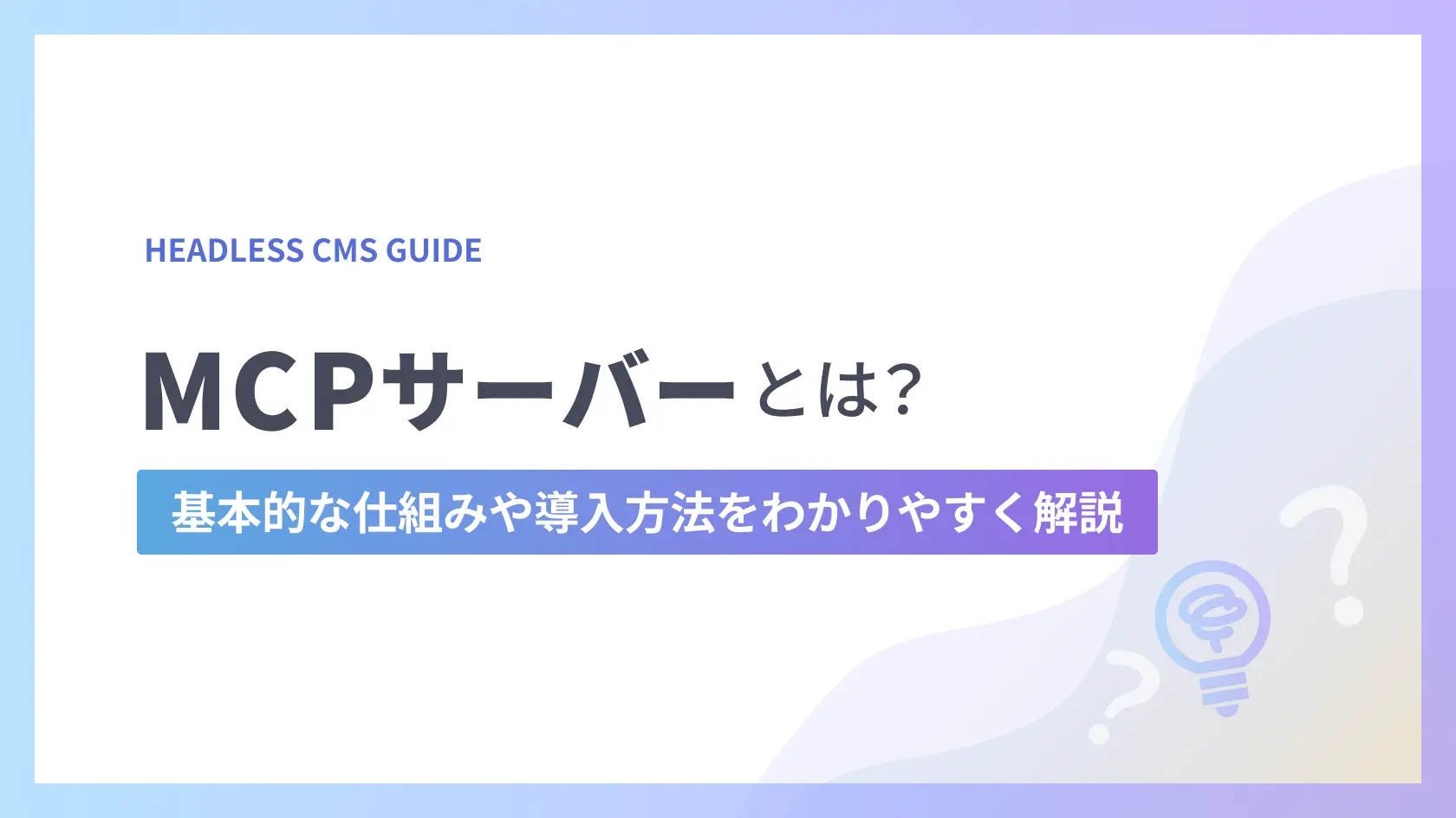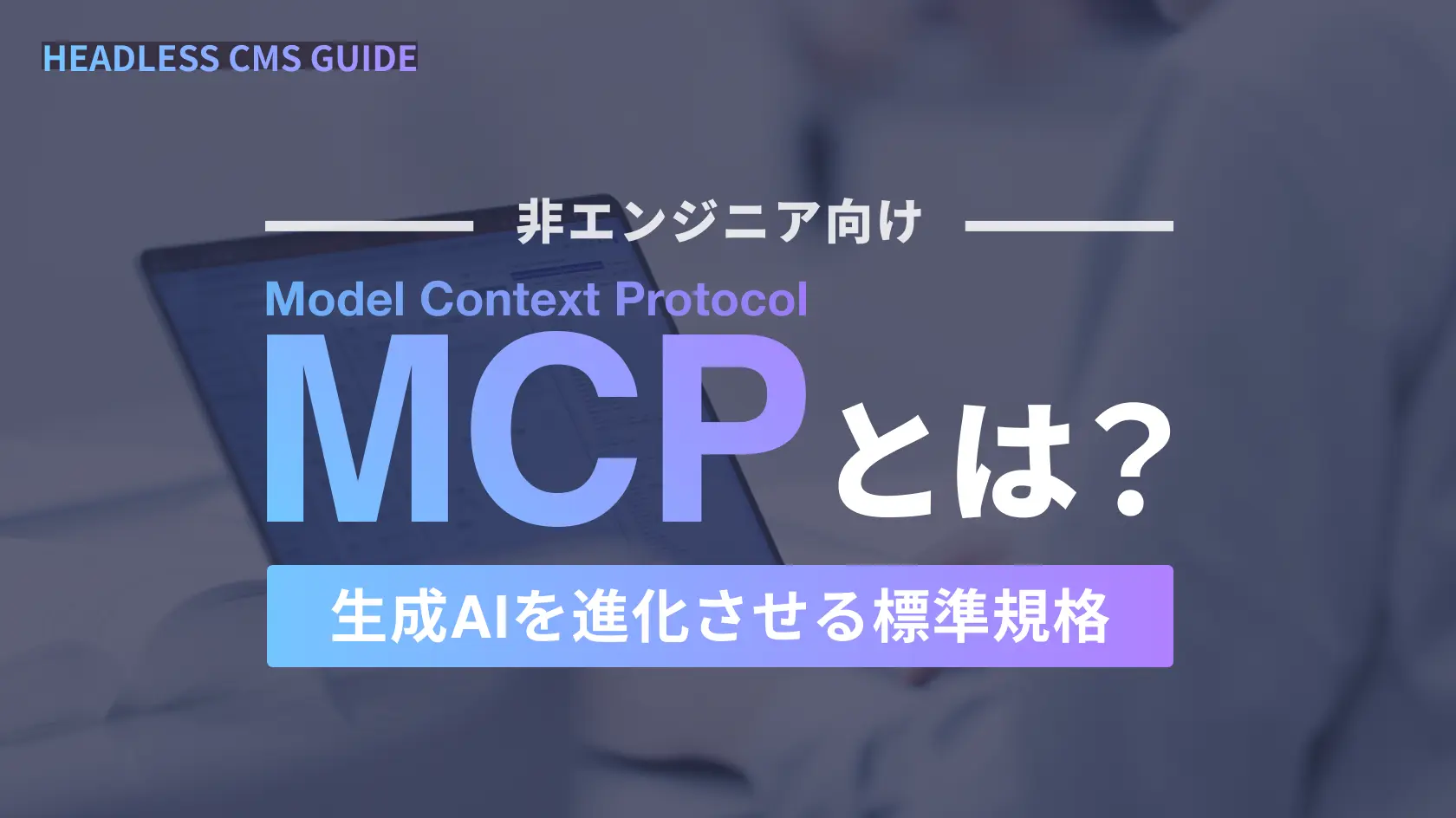記事入稿も、公開予約も、AIで。
人とAIの理想的な協業体制を実現するヘッドレスCMS「NILTO」
コンテンツ運用の「時間不足」「アイデア枯渇」「人手不足」をAIが解決。
フェンリルの国産ヘッドレスCMS『NILTO』新機能「NILTO
MCP」はAIエージェントと協業して情報収集から入稿・承認・公開予約まで自動化し、リードタイムとコストを削減。
現在全プランでテクニカルプレビュー提供中。
今ならあなたのフィードバックがNILTOに反映されるチャンスです。
目次
なぜウェブサイト高速化が重要なのか
ウェブサイトの表示速度は、「快適さ」だけの問題ではありません。 ユーザーの行動、検索エンジンの評価、ビジネスの成果にまで、大きな影響を与える重要な要素です。
このセクションでは、高速化が重要視される3つの理由を解説します。
理由1. ユーザー体験の向上につながる
現代のユーザーは、素早い情報取得を求めています。 ページの読み込みが遅いと、多くのユーザーはコンテンツを見る前にサイトを離れてしまいます。
実際に、読み込み時間が長いほど、ユーザーの離脱率は高まります。 快適なブラウジング体験を提供することは、ユーザーにコンテンツを確実に届け、サイトに長く滞在してもらうための基本的な要件です。
理由2. SEO評価の向上につながる
Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザー体験の質を検索ランキングの重要な要素としています。
サイトの表示速度もその一つです。 特に「Core Web Vitals(コア ウェブ バイタル)」という指標を用いて、ページの読み込み速度、応答性、視覚的安定性を評価しています。 Core Web Vitalsとは、Googleが定めたウェブサイトのユーザー体験を測る3つの重要な指標のことです。
表示速度が速いサイトは、ユーザー体験が良いと判断されます。 その結果、検索結果で上位に表示されやすくなります。
これは、より多くの潜在顧客にサイトを見つけてもらうための重要な要素です。
理由3. コンバージョン率改善につながる
ウェブサイトの目的が商品購入や問い合わせ、資料請求などのコンバージョンである場合、表示速度は達成率に直接影響します。 コンバージョンとは、サイト訪問者が目的のアクション(購入・問い合わせなど)を実行することを指します。
ページ表示が遅いECサイトでは、ユーザーは購入プロセス完了前に離脱する可能性が高まります。 一方、スムーズで速いサイトはユーザーのストレスを軽減し、購買意欲を高めます。
サイトの高速化は、ユーザー体験向上だけでなく、ビジネスの売上向上につながる費用対効果の高い投資です。
ウェブサイトの表示速度を計測する方法
ウェブサイトの高速化に取り組む前に、現状のパフォーマンスを正確に把握することが重要です。
ここでは、Googleが提供する信頼性の高い無料ツールを使った計測方法を解説します。 これらのツールで、サイトの表示速度を測定し、具体的な問題点を特定できます。
Google PageSpeed Insightsの活用
PageSpeed Insightsは、ウェブページのURLを入力するだけで、パフォーマンスを簡単に診断できるツールです。
モバイル環境とデスクトップ環境の両方でパフォーマンススコアを測定できます。 Core Web Vitalsの評価も明確に表示されます。 診断結果では、具体的な改善点がリストアップされます。 各改善による時間短縮の予測も示されるため、改善策の優先順位を判断するのに役立ちます。
Lighthouseの活用
Lighthouseは、Google Chromeブラウザに標準で組み込まれている開発者向けツールの一部で、より詳細なパフォーマンス分析が可能です。
PageSpeed Insightsが提供する情報に加えて、アクセシビリティ、SEO、プログレッシブウェブアプリ(PWA)の基準を満たしているかなど、サイトの品質を多角的な観点から評価します。技術的な詳細情報が豊富で、開発者がパフォーマンス問題の根本原因を特定するのに非常に有効なツールです。
計測結果の基本的な見方
これらのツールで表示されるパフォーマンススコアは、0から100の数値で示され、数値が高いほどパフォーマンスが良いことを意味します。
特に注目すべきは、Core Web Vitalsの各指標(LCP, INP, CLS)が「良好(緑)」、「改善が必要(黄)」、「不良(赤)」のいずれで評価されているかです。また、「改善できる項目」セクションに表示される提案は、具体的なアクションにつながる重要な情報源となります。これらの提案を一つずつ確認し、改善策を検討していくことが、高速化への着実な一歩となります。
ウェブサイトを高速化する具体的な方法
サイトの現状を把握したら、次はいよいよ具体的な改善策を実行するフェーズです。
ここでは、多くのウェブサイトで共通して効果の高い、基本的な高速化手法を3つのカテゴリーに分けて、その仕組みと共に詳しく解説します。
画像の最適化
ウェブページの中で最もデータ容量を占めることが多い要素が画像です。そのため、画像を最適化するだけで、サイト全体の表示速度は劇的に改善されることが少なくありません。
ファイルサイズの圧縮
画質を大きく損なうことなく、画像のファイルサイズを小さくすることが重要です。多くの画像編集ツールやオンラインサービスで圧縮が可能で、一般的には品質を70~80%程度に設定することが推奨されます。
これは、人間の目にはほとんど知覚できないレベルの画質劣化と引き換えに、ファイルサイズを大幅に削減する処理です。見た目の変化がほとんどない範囲で、可能な限りファイルサイズを削減しましょう。
次世代フォーマット(WebP, AVIF)の利用
JPEGやPNGといった従来の画像フォーマットよりも、新しいフォーマットであるWebPや、さらに新しいAVIFは、画質を保ったまま、より高い圧縮率を実現します。これにより、ファイルサイズを大幅に削減することが可能です。
すべてのブラウザがこれらの新しいフォーマットに対応しているわけではないため、HTMLの<picture>タグを使用するのが一般的です。このタグを使うことで、対応ブラウザにはWebPやAVIFを、非対応ブラウザには従来のJPEGやPNGを表示させるといった、最適な画像配信を自動的に行うことができます。
遅延読み込み(Lazy Loading)の実装
ページ上のすべての画像を一度に読み込むのではなく、ユーザーがスクロールして画像が表示領域(ビューポート)に入る直前まで、その画像の読み込みを遅らせる手法です。これにより、ページの初期読み込みに必要なデータ量が減り、ユーザーがコンテンツを体感する速度が大幅に向上します。
特に、縦に長いページや画像が多く使われているページで非常に効果的です。現在では、loading='lazy'というHTML属性を指定するだけで、簡単に実装できます。
レスポンシブイメージの実装
ユーザーが閲覧しているデバイスの画面サイズや解像度に応じて、最適なサイズの画像を表示する手法です。
例えば、PCの大画面では高解像度の大きな画像を、スマートフォンの小さな画面ではそれに応じたファイルサイズの小さな画像を表示します。これにより、モバイルユーザーが不要に大きな画像をダウンロードすることを防ぎ、表示速度を向上させることができます。HTMLのsrcset属性やsizes属性を使い、複数の画像候補をブラウザに提示することで実装します。
CSS・JavaScriptの最適化
CSS(スタイルシート)やJavaScriptは、Webサイトの見た目や動的な機能を制御する重要な要素ですが、これらが表示速度のボトルネックになることも少なくありません。
ファイルの圧縮と最小化(Minify)
CSSやJavaScriptのファイルから、人間が読みやすくするために記述されたスペース、改行、コメントなどをプログラムで自動的に削除し、ファイルサイズを極限まで小さくすることを「最小化(Minify)」と呼びます。これにより、ファイルのダウンロード時間を短縮できます。
多くの開発ツールには、この処理を自動で行う機能が備わっており、Webサイト公開時の標準的なプロセスの一つとなっています。
不要なコードの削除
サイトの改修を重ねるうちに、過去には使っていたものの、現在は使われなくなったCSSのスタイルやJavaScriptの機能がファイル内に残ってしまうことがあります。これらの不要なコードは、わずかであってもページの読み込みや処理の遅延につながるため、定期的に見直して削除することが重要です。
Google Chromeの開発者ツールなどを使って、ページ表示時に実際に使用されているコードの割合を特定し、不要なコードを洗い出すことができます。
レンダリングを妨げるリソースの除外
ブラウザがページを表示する際、CSSやJavaScriptの読み込みが完了するまで、ページの表示処理を中断してしまうことがあります。これを「レンダリングブロック」と呼びます。
特に、ページの初期表示に直接関係のないJavaScript(例えば、ページのフッターで使われる分析ツールなど)は、ページの主要なコンテンツが読み込まれた後に非同期で読み込むように設定することで、ユーザーがコンテンツを早く見られるようになります。deferやasyncといったHTML属性を利用して制御します。
サーバー・インフラの改善
ユーザーが快適にサイトを閲覧するためには、コンテンツを配信するサーバー側の環境、つまりインフラストラクチャも非常に重要です。
サーバー応答時間の短縮
ブラウザがサーバーにリクエストを送ってから、最初のデータが返ってくるまでの時間(TTFB - Time to First Byte)が長いと、その後のすべての処理が遅れてしまいます。
これは、サーバーの処理能力が不足している場合や、データベースへの問い合わせが非効率な場合に発生します。
利用しているサーバーのスペックを見直したり、Webアプリケーションのプログラムを改善したりすることが有効な対策となります。
CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の活用
CDNは、世界中に分散配置されたサーバーのネットワークです。ウェブサイトのコンテンツ、特に画像やCSS、JavaScriptといった静的なファイルのコピーをこれらのサーバーに配置します。
そして、ユーザーからのアクセスがあった際に、そのユーザーに物理的に最も近いサーバーからコンテンツを配信することで、通信の遅延を大幅に削減します。これにより、世界中のどこからアクセスしても、安定した速さでコンテンツを届けることが可能になります。
ブラウザキャッシュの有効化
一度サイトを訪れたユーザーが再度アクセスした際に、前回ダウンロードしたCSSや画像、JavaScriptなどのファイルを、再度サーバーからダウンロードするのではなく、ユーザーのコンピュータ(ブラウザ)に保存されているものを再利用する仕組みです。
これにより、2回目以降の訪問時の表示速度が大幅に向上し、サーバーの負荷も軽減されます。サーバーの設定で、ファイルの種類ごとにキャッシュを有効にする期間(例:画像は1年間、CSSは1週間など)を指定することが一般的です。
モダンなウェブサイト高速化のアプローチ
基本的な高速化手法に加えて、近年のウェブ開発では、サイトのアーキテクチャ(構造)そのものからパフォーマンスを徹底的に追求するアプローチが主流になっています。
ここでは、特に効果の高い2つのモダンなアプローチを紹介します。
ヘッドレスアーキテクチャの採用
従来のCMS(WordPressなど)では、コンテンツを管理するバックエンドと、それを表示するフロントエンドが一体化していました。
これに対し、ヘッドレスCMSは、コンテンツ管理機能のみを提供し、表示方法はAPIを通じて自由に開発できるアーキテクチャです。この「バックエンドとフロントエンドの分離」により、フロントエンドではReactやVue.jsといった最新の高速な技術を制約なく採用でき、パフォーマンスに最適化されたサイト構築が可能になります。
バックエンドの処理が表示速度に直接影響を与えにくくなるため、構造的に高速化しやすいのが大きな利点です。
静的サイト生成(SSG/ISR)の活用
静的サイト生成(SSG - Static Site Generation)は、ヘッドレスCMSと組み合わせて使われることが多い最先端の技術です。
ユーザーからリクエストがあるたびにサーバーでページを生成するのではなく、ウェブサイトの公開前に、あらかじめすべてのページをHTMLファイルとして生成しておきます。ユーザーは、この完成済みのHTMLファイルを受け取るだけなので、サーバーでの処理が一切不要になり、CDNと組み合わせることで驚異的な表示速度を実現します。
また、ISR(Incremental Static Regeneration)という手法を使えば、定期的に、またはコンテンツが更新されたタイミングでページを再生成し、静的サイトの速さと動的サイトの更新性を両立させることも可能です。
ウェブサイト高速化のよくある質問
ウェブサイトの高速化に関して、担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
AMP対応は必須か
AMP(Accelerated Mobile Pages)は、モバイルページの表示を高速化するためにGoogleが主導していたフレームワークです。一時期はSEOに有利とされていましたが、現在ではAMPでなくてもCore Web Vitalsの基準を満たしていれば、検索順位において同等に評価されるようになっています。AMPの導入には独自の仕様に合わせた開発・運用コストがかかるため、現在では必須の技術とは言えません。
まずは本記事で紹介したような基本的な高速化施策を優先し、リソースに余裕があれば検討するのが良いでしょう。
高速化に最適な画像サイズは
一概に「このサイズが最適」という絶対的な正解はありません。重要なのは、ウェブページ上でその画像が表示される領域に対して、大きすぎない、適切なサイズの画像を用意することです。
例えば、ページの横幅いっぱいに表示されるメイン画像と、記事一覧で使われる小さなサムネイル画像では、必要な画像の寸法(ピクセル数)は全く異なります。レスポンシブイメージの手法を使い、デバイスの画面サイズや解像度に応じて複数のサイズの画像を用意し、ブラウザに最も最適なものを選択させることが理想的なアプローチです。
プラグインの入れすぎは速度に影響するか
結論から言うと、大きく影響します。特にWordPressなどのCMSでプラグインを多用すると、表示速度が低下する主要な原因となり得ます。
これは、プラグインがそれぞれ独自のCSSやJavaScriptを追加で読み込んだり、サーバーでの処理を増やしたりするためです。サイトに必要な機能かを見極め、使っていないプラグインは無効化するだけでなく、サーバーから完全に削除することが重要です。
また、同様の機能を持つプラグインが複数ある場合は、より軽量で、コミュニティでの評価が高いものを選ぶようにしましょう。
ヘッドレスCMSにすれば必ず速くなりますか
いいえ、必ず速くなるとは限りません。ヘッドレスCMSは、高速なサイトを構築するための「可能性」を飛躍的に高めるアーキテクチャですが、魔法の杖ではありません。その利点を最大限に活かすには、パフォーマンスを常に意識した、適切なフロントエンドの設計と開発が不可欠です。
例えば、静的サイト生成(SSG)のような高速化技術を採用したり、画像の最適化を自動化する仕組みをフロントエンドのビルドプロセスに組み込んだりすることで、初めてその真価が発揮されます。単にヘッドレスCMSを導入しただけでは、期待したほどの速度向上は得られない可能性があります。
最後に
ウェブサイトの高速化は、一度行えば終わりというものではありません。新しいコンテンツの追加や機能の拡張、あるいは時間の経過とともに、サイトのパフォーマンスは常に変化します。
今回ご紹介した方法を参考に、まずはPageSpeed Insightsなどのツールで自社サイトの現状を正確に把握し、改善インパクトの大きいところから着手してみてください。そして、定期的にパフォーマンスを計測し、継続的に改善を続けることが、ユーザーに愛され、ビジネスを成長させるウェブサイトを維持するための、最も確実な道筋です。
記事入稿も、公開予約も、AIで。
人が行う作業にサヨナラできるヘッドレスCMS「NILTO」
コンテンツ運用における 「時間がない」「アイデアが枯渇した」「人手が足りない」 といったお悩みはありませんか?
これからのコンテンツ管理は、AIエージェントがサポートする時代です。
フェンリルが提供する国産ヘッドレスCMS『NILTO』の新機能 「NILTO MCP(Model-Context-Protocol)」は、 AIエージェントによる高度なコンテンツ運用の自動化を可能にします。
プロンプトの指示で情報収集から原稿入稿、承認依頼、公開予約までを一気通貫で対応し、 施策にかかるリードタイムと作業コストを劇的に削減します。
現在は、テクニカルプレビューとして全プランでご利用いただけます。
皆様が利用されたフィードバックを元にブラッシュアップを行っていますので、 今ご利用いただければ、あなたの貴重なご意見がNILTOに反映されるチャンスです。
このタイミングでぜひご利用ください。