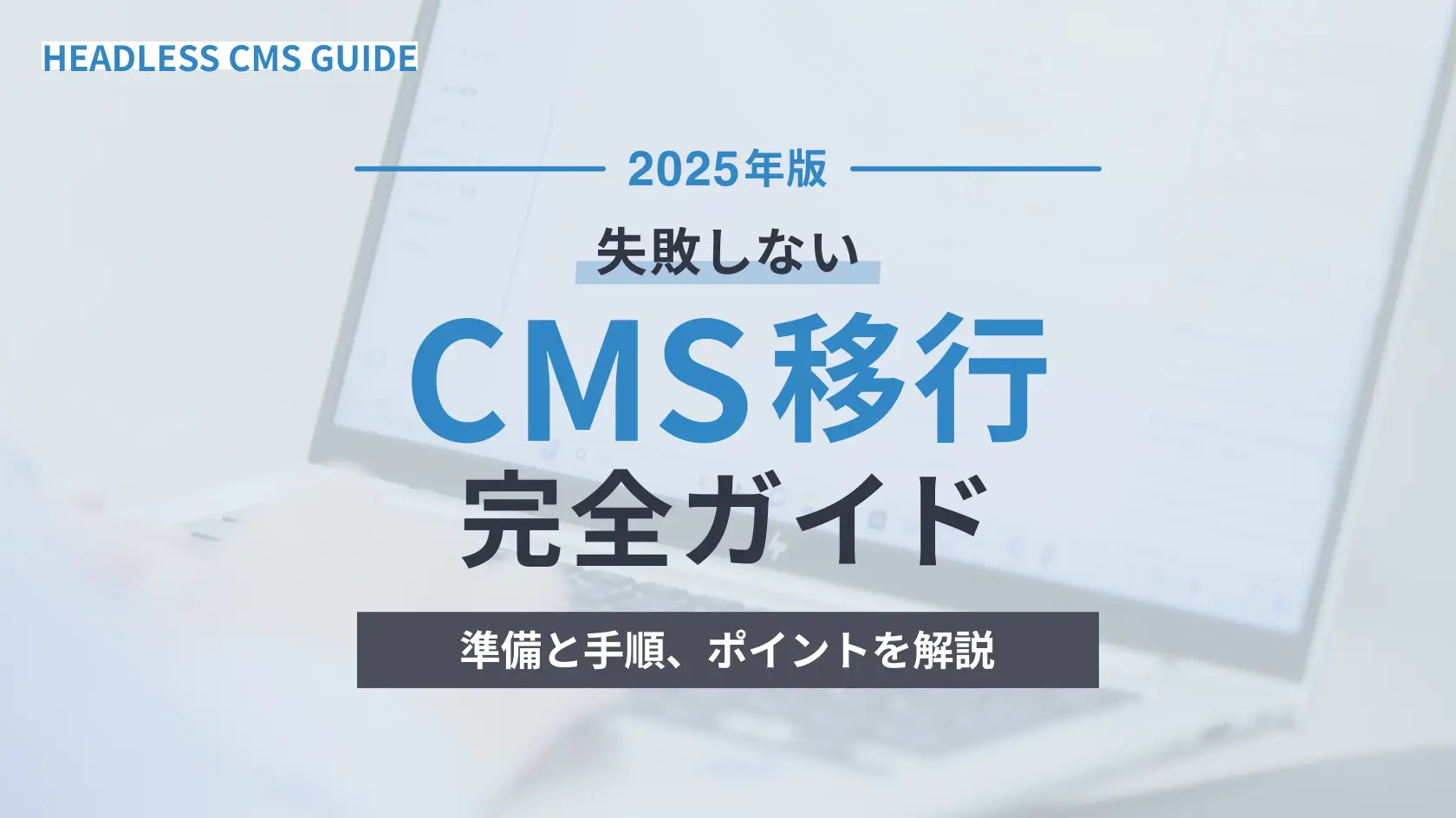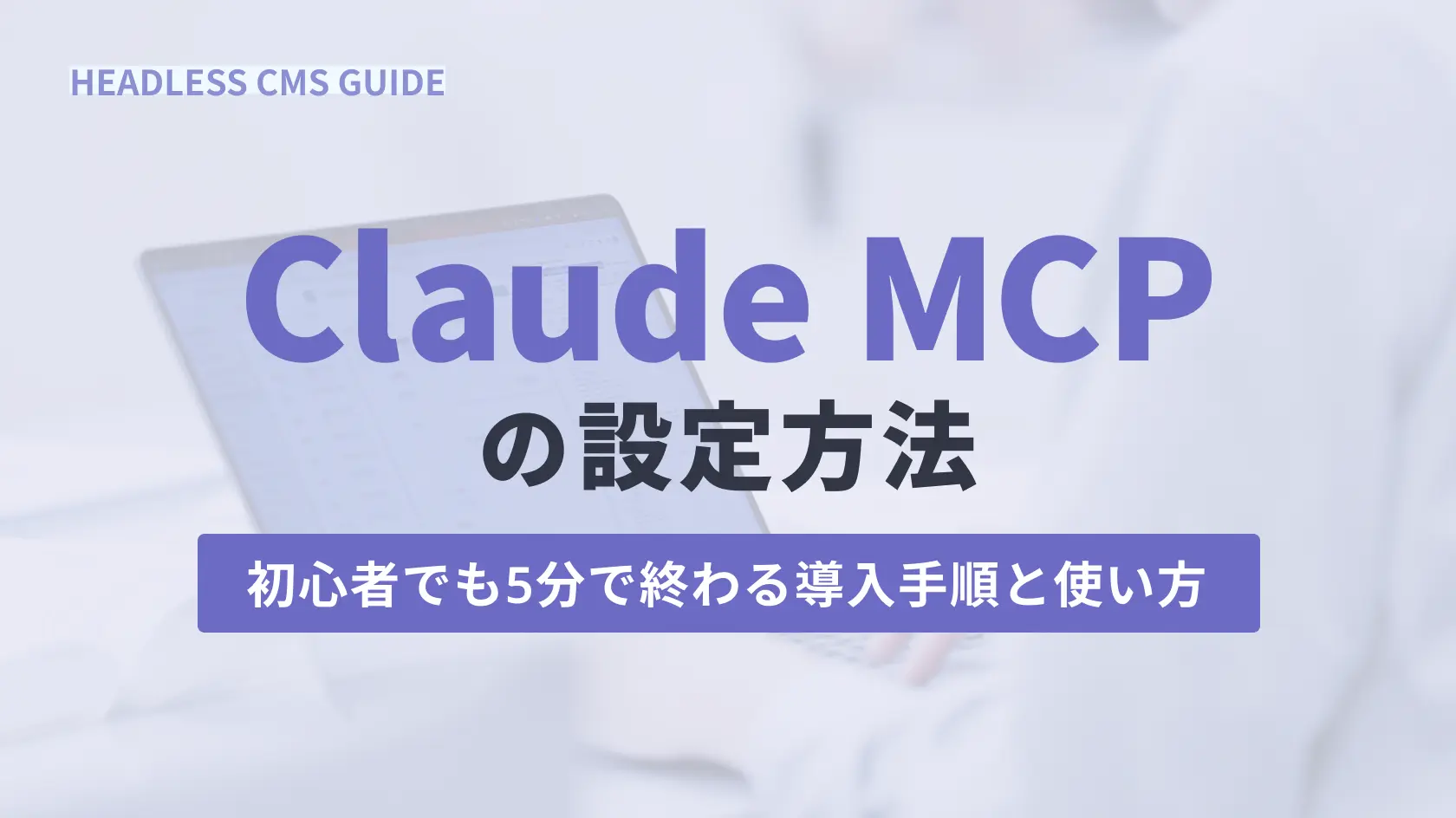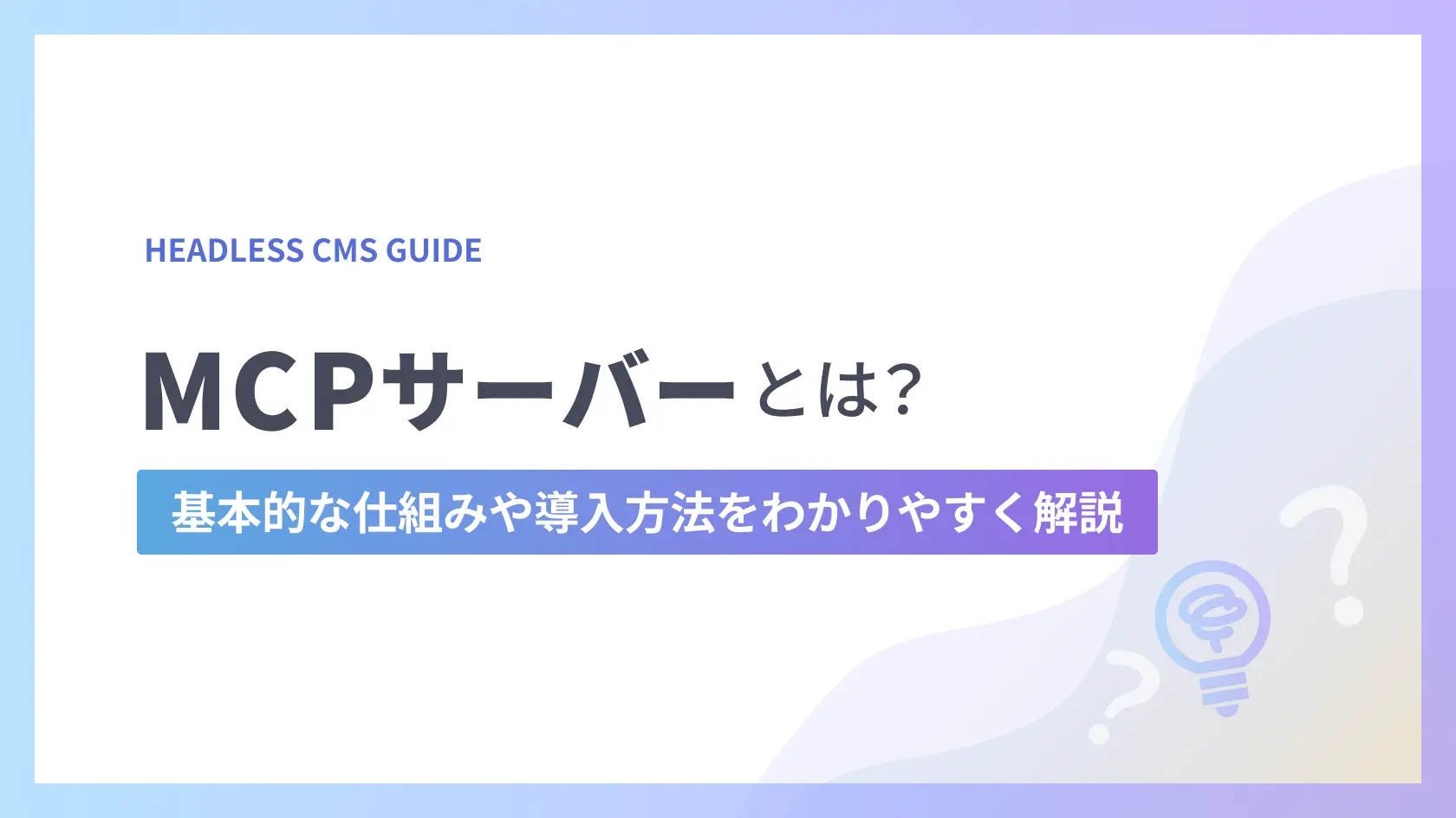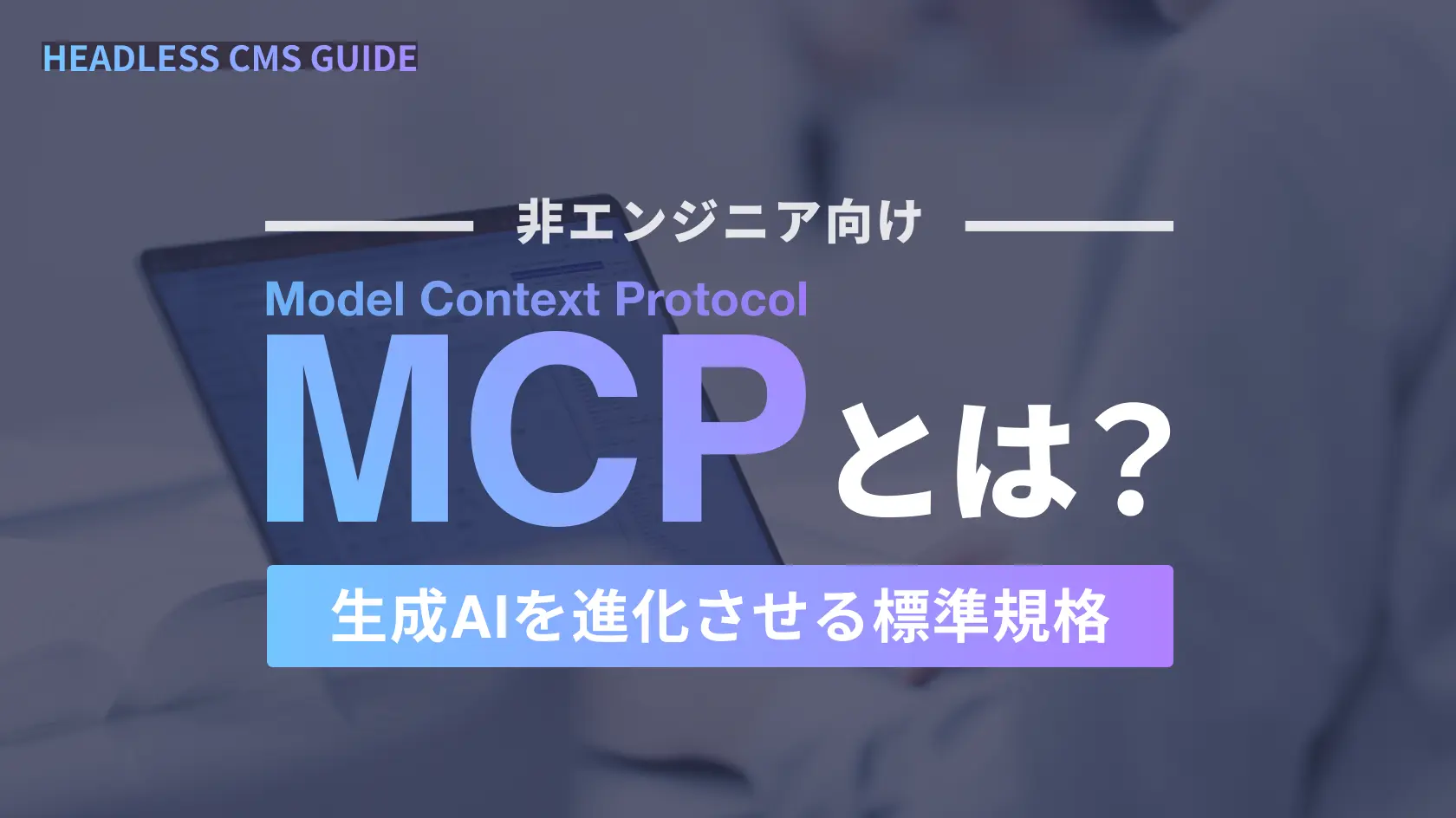記事入稿も、公開予約も、AIで。
人とAIの理想的な協業体制を実現するヘッドレスCMS「NILTO」
コンテンツ運用の「時間不足」「アイデア枯渇」「人手不足」をAIが解決。
フェンリルの国産ヘッドレスCMS『NILTO』新機能「NILTO
MCP」はAIエージェントと協業して情報収集から入稿・承認・公開予約まで自動化し、リードタイムとコストを削減。
現在全プランでテクニカルプレビュー提供中。
今ならあなたのフィードバックがNILTOに反映されるチャンスです。
目次
移行前の準備|CMSの4タイプを紹介
CMSは提供形態やアーキテクチャによって4つのタイプに分類されます。最適なCMSを選定するには、まずCMSの種類と特徴を理解し、自社の要件に照らし合わせて評価することが重要です。
ここでは4つの主要なCMSタイプと、選定時の6つの比較ポイントを解説します。それぞれの特性を理解することで、自社に最適な選択が可能になります。
CMSの4タイプと特徴
CMSは、その提供形態やアーキテクチャによって、大きく4つのタイプに分類されます。それぞれの特性を深く理解し、自社のリソース、目的、将来の展望に最も合致するものを選びましょう。
1. オープンソースCMS
- 概要
WordPressに代表される、ソースコードが無償で公開されているCMSです。世界中の開発者によるコミュニティによって開発・維持されており、誰でも自由に利用・改変・再配布が可能です。豊富なデザインテーマや機能拡張のためのプラグインがエコシステムとして形成されているのが大きな特徴です。
- メリット・デメリット
最大のメリットは、ライセンス費用が不要である点です。またプラグインなどを活用して機能を柔軟に拡張できるカスタマイズ性の高さも魅力です。
一方で、サーバーの構築や保守、セキュリティ対策は全て利用者の自己責任となります。公式のサポート窓口は存在せず、問題解決はコミュニティフォーラムやWeb上の情報に頼ることになります。そのため専門的な技術知識が不可欠です。
- 向いてるケース
社内に技術者がいる場合や、信頼できる外部パートナーを確保できる場合に適しています。コストを抑えつつ独自の機能やデザインを実装したいスタートアップや中小企業、オウンドメディア、個人のブログなどで広く採用されています。
2. パッケージCMS
- 概要
特定のITベンダーが独自に開発し、商用ライセンスとして販売するCMS製品です。従来は自社で管理するサーバーにインストールするオンプレミス型が主流でしたが、近年ではベンダーが提供するクラウド環境で利用できるサービスも増えています。
- メリット・デメリット
企業利用を前提とした豊富な機能、手厚い公式サポート、高いセキュリティレベルがメリットです。システムの脆弱性に対する責任もベンダーが負うため、安心して運用できます。その反面、高額なライセンス費用や年間の保守費用が発生します。
また、機能のカスタマイズはベンダーに依存するため、オープンソースほどの自由度はありません。さらに、システムが特定ベンダーの独自技術で構築されている場合が多く、将来他のシステムへの移行が技術的に困難になる可能性があります。
- 向いてるケース
個人情報や決済情報を扱う大規模なECサイトに最適です。金融機関や官公庁の公式サイトなど、システムの信頼性やセキュリティ、コンプライアンスが最優先される場合にも適しています。専任の担当者による迅速なサポートを必要とする企業にも向いています。
3. クラウドCMS
- 概要
サーバーの準備が不要で、インターネットを通じてサービスとして提供されるCMS(SaaS)です。利用者は月額や年額で利用料を支払うことで、すぐにCMSを使い始めることができます。システムの保守やアップデート、セキュリティ管理は全てサービス提供元であるベンダーが行います。
- メリット・デメリット
導入の手軽さと、サーバー管理が不要なことによる運用負荷の低減が最大のメリットです。初期費用を抑え、迅速にサイトを立ち上げたい場合に非常に有効です。ただし、提供される機能やデザインの範囲内でのサイト構築となるため、カスタマイズの自由度は他のタイプに比べて低い傾向にあります。
また、データや運用をサービス提供元に委ねるため、将来サービスを乗り換えようとしてもデータの移行が困難であったり、提供元のサービス終了や大幅な料金改定といった事業方針に、自社のサイト運用が左右されたりするリスクには注意が必要です。
- 向いてるケース
専門のIT部門を持たない企業や、とにかく早くWebサイトを公開したい場合に適しています。企業のコーポレートサイト、期間限定のキャンペーンサイト、スタートアップのサービスサイトなど、運用負荷をかけずにスピーディな情報発信を行いたい場合に最適です。
4. ヘッドレスCMS
- 概要
コンテンツを管理する「バックエンド」と、ユーザーに表示される「フロントエンド(ヘッド)」を完全に分離したアーキテクチャを持つ次世代のCMSです。
管理画面で作成したコンテンツはAPIを通じて配信され、Webサイトだけでなく、スマートフォンアプリ、デジタルサイネージ、IoTデバイスなど様々な表示先で利用できます。
- メリット・デメリット
APIを介してコンテンツを配信するため、フロントエンドの技術選定に制約がなく、開発の自由度が非常に高い点がメリットです。またチャネルごとにコンテンツを管理する必要がなく、効率的な情報発信が可能です。
一方で、フロントエンドを別途開発する必要があるため、専門的な技術力と相応の開発コストが求められます。
- 向いてるケース
Webサイト以外にもスマートフォンアプリなど、複数のチャネルで一貫した情報を発信したいオムニチャネル戦略を推進する企業に最適です。また表示速度やUI/UXにこだわり、最新の技術スタックでフロントエンドを構築したい技術力の高い開発チームを持つ企業にも向いています。
選定時の6つの比較ポイント
最適なCMSを選定するには、以下の6つの観点で総合的に評価することが重要です。
1. 機能
自社の要件を満たす機能が揃っているか
2. 費用
初期費用と運用費用のバランスは適切か
3. セキュリティ
必要なセキュリティレベルを確保できるか
4. サポート体制
トラブル時の対応体制は十分か
5. 操作性
担当者が日常的に使いこなせるか
6. 拡張性
将来的な機能追加や改修に対応できるか
そして、これら6つの軸と同じく重要なのが「自社の運用体制に合っているか」という視点です。例えば、専門のIT担当者がいない体制で開発の自由度が高いヘッドレスCMSを選んでも、その能力を十分に引き出すことは困難です。
日々の更新は誰が行うのか、その担当者のITスキルはどの程度かといった自社の「人」の側面と照らし合わせて評価することが、移行後のスムーズな運用を実現する最後の鍵となります。
失敗しないCMS移行の5ステップ
CMSの移行を成功させるには、体系化されたプロセスに沿って計画的に進めることが不可欠です。ここでは、実践的な5つのステップを詳しく解説します。
ステップ1:要件定義とコンテンツ整理
移行プロジェクトの最初のステップは、新しいWebサイトとCMSに求められる要件を定義することです。同時に移行する資産(コンテンツ)の範囲を明確にします。この工程はプロジェクト全体の設計図となり、後のCMS選定や開発における判断基準となります。
要件定義では、現行サイトの課題解決はもちろん、将来の事業展開も見据えます。必要な機能や達成すべき性能、担保すべきセキュリティレベルなどを具体的に言語化します。
同時に既存サイトの全ページをリストアップし、アクセス解析データや事業への貢献度を基に「コンテンツ棚卸し」を実施します。移行するコンテンツ、削除するコンテンツ、内容を更新するコンテンツを精査することで、移行作業のスコープが確定し、無駄な作業を削減できます。
ステップ2:CMSの選定と比較検討
ステップ1で定義した要件を基に、市場に存在する複数のCMSを比較検討し、最適なプラットフォームを選定します。選定にあたっては、各CMSの機能が要件をどの程度満たすかはもちろんのこと、ライセンス費用や保守費用を含めたトータルコスト、ベンダーによるサポート体制、セキュリティの堅牢性、そして実際にコンテンツを更新する担当者の操作性まで、多角的な視点で評価することが肝要です。
失敗しない費用計画の立て方
CMS移行の費用は、プロジェクトの規模や要件によって大きく変動します。ここでは、費用を左右する4つの要因と、適切な費用計画を立てるためのポイントを解説します。
1. プロジェクト管理費
進捗管理や関係者調整にかかる費用です。プロジェクト規模が大きいほど高額になります。
2. 設計費
要件定義やシステム設計にかかる費用です。複雑な要件ほど設計工数が増加します。
3. CMS構築・設定費
新CMSの環境構築やカスタマイズにかかる費用です。オリジナル機能の開発が必要な場合は高額になります。
4. データ移行費
既存コンテンツの移行にかかる費用です。ページ数が多い場合や自動化プログラムが必要な場合は費用が増加します。
正確な見積もりを取得する3つの準備
精度の高い見積もりを得るには、以下の準備が必要です。
1. 要件定義書の作成
新CMSに求める機能や性能を明文化します。
2. コンテンツ棚卸しリストの作成
移行対象となるページ数や種類を一覧化します。
3. 複数社への相見積もり
3社以上から見積もりを取得し、費用と提案内容を比較検討します。
初期費用と運用費用(TCO)の視点
移行時に発生する「初期費用」だけでなく、移行後に継続的にかかる「運用費用」まで含めたTCO(総所有コスト)で費用を評価する視点も不可欠です。
例えば、初期費用が安価なオープンソースCMSは、その後のセキュリティ対策やサーバーメンテナンスに別途費用や人的コストがかかる場合があります。一方で、月額費用が発生するクラウドCMSは、初期費用を抑えつつ保守・運用コストを平準化できます。
目先の金額だけで判断せず、長期的な視点で最もコストパフォーマンスに優れた選択をすることが、賢明な費用計画と言えるでしょう。
ステップ3:移行計画の策定と体制構築
CMSの選定が完了したら、具体的な移行プロジェクトの計画を策定します。誰が、いつまでに、何を、どのように行うのかを詳細に定義したWBS(作業分解構成図)やガントチャートを作成し、プロジェクトの全体像とマイルストーンを可視化します。また、プロジェクトマネージャー、コンテンツ移行担当者、開発担当者、テスト担当者など、必要な役割を明確にし、プロジェクトを推進するための体制を構築します。
外部の制作会社や開発ベンダーに依頼する場合は、この段階で契約内容を詳細に詰め、双方の責任範囲を明確にした上で契約を締結することが、後のトラブルを未然に防ぎます。
ステップ4:データ移行とシステム構築
策定した計画に従い、実際の移行作業に着手します。このステップでは、新しいCMSをサーバーにインストールし、必要な設定を行うシステム構築と、既存サイトからコンテンツを移管するデータ移行を並行して進めます。
データ移行の方法は、手作業でコピー&ペーストする方法から、CSVファイルで一括インポートする方法、移行用のプログラムを開発して自動化する方法まで様々です。サイトのデザインリニューアルを同時に行う場合は、新しいデザインテンプレートの開発やフロントエンドのコーディングもこの段階で実施します。
ステップ5:テストと公開前チェック
構築とデータ移行が完了したサイトは、すぐに公開するのではなく、テスト環境で入念な品質チェックを行います。表示崩れや誤字脱字のチェックはもちろん、リンクが正しく機能するか、お問い合わせフォームなどのプログラムが正常に動作するか、複数のブラウザやデバイスで表示が崩れないかなど、あらゆる観点から検証します。
特に、URLを変更したページについては、SEO評価を引き継ぐための301リダイレクトが正しく設定されているかの確認が極めて重要です。全てのテスト項目をクリアし、品質が担保されたことを確認した上で、初めて本番環境への公開となります。
失敗を防ぐ3つのポイント
CMS移行プロジェクトでの失敗を防ぐため、特に重要な3つのポイントに焦点を当てて解説します。これらの対策を事前に講じることで、プロジェクトの成功確率を大幅に高めることができます。
ポイント1. SEO評価の低下を防ぐURLの取り扱い
CMS移行における最大の技術的リスクの一つが、URLの変更に伴う検索エンジンからの評価(SEO評価)の低下です。検索エンジンはURL単位でページを評価しているため、URLが変更されると、それまで蓄積してきた評価がリセットされてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、可能な限りURLを変更しないことが最善の策です。やむを得ず変更する場合は、旧URLから新URLへ恒久的な転送を示す「301リダイレクト」をページ単位で正確に設定し、検索エンジンにページの移転を正しく伝える必要があります。この対応を怠ると、検索順位の大幅な下落や検索結果からの消失を招く恐れがあります。
ただし、サイト構造が複雑化している場合など、専門家の管理下でURL構造を整理・最適化し、ページ評価の向上を狙う高度な戦略を取ることもあります。いずれのケースにおいても、301リダイレクトによる適切な処置が不可欠であることに変わりはありません。
ポイント2. データ消失に備えるバックアップの徹底
移行作業には、人的な操作ミスやシステムの予期せぬエラーが付き物です。万が一の事態が発生した際に、元の状態に復旧できなければ、事業に深刻な損害を与えかねません。
このような最悪の事態を避けるため、移行作業に着手する前には、必ずWebサイトの全データ(ファイル、データベース)の完全なバックアップを取得し、安全な場所に保管してください。
また、作業の区切りが良いタイミングで、段階的にバックアップを取得することも、リスク管理の観点から非常に有効です。
さらに万全を期すのであれば、取得したバックアップデータを用いて、実際にサイトを復元できるかどうかの「復元テスト」を事前に別の環境で実施しておくことが理想的です。これにより、「バックアップは取ったが、データが破損していて使えなかった」という最悪の事態を防ぐことができます。
ポイント3. プロジェクトを円滑に進める体制・計画
捗報告、外部ベンダーとの連携など、多岐にわたるコミュニケーションが発生します。プロジェクトを円滑に進めるためには、役割と責任が明確なチームを組織し、現実的で余裕を持ったスケジュールを策定することが不可欠です。
定期的な進捗会議を通じて課題を早期に発見・共有し、関係者全員が同じ目標に向かって協力できる体制を整えることが、プロジェクト成功の鍵となります。
まとめ|CMS移行の成功に向けて
本記事では、CMS移行を成功させるための具体的な5つのステップ、プロジェクトを失敗させないための重要な注意点、そして自社に最適なCMSを選び抜くための比較ポイントから費用相場まで、網羅的に解説しました。
CMS移行は、決して単なるシステムの入れ替え作業ではありません。 それは、Webサイトが抱える根本的な課題を解決し、将来の事業成長の基盤を再構築するための戦略的な投資です。プロジェクトの道のりには、技術的な課題や関係者との調整など、多くの困難が伴うかもしれません。
しかし、一つひとつのステップを丁寧に進め、起こりうるリスクを事前に把握し対策を講じることで、その成功確率は飛躍的に高まります。まずは、本記事で解説した「要件定義とコンテンツ整理」から着手し、自社の現状を客観的に把握することから始めてみてください。
記事入稿も、公開予約も、AIで。
人が行う作業にサヨナラできるヘッドレスCMS「NILTO」
コンテンツ運用における 「時間がない」「アイデアが枯渇した」「人手が足りない」 といったお悩みはありませんか?
これからのコンテンツ管理は、AIエージェントがサポートする時代です。
フェンリルが提供する国産ヘッドレスCMS『NILTO』の新機能 「NILTO MCP(Model-Context-Protocol)」は、 AIエージェントによる高度なコンテンツ運用の自動化を可能にします。
プロンプトの指示で情報収集から原稿入稿、承認依頼、公開予約までを一気通貫で対応し、 施策にかかるリードタイムと作業コストを劇的に削減します。
現在は、テクニカルプレビューとして全プランでご利用いただけます。
皆様が利用されたフィードバックを元にブラッシュアップを行っていますので、 今ご利用いただければ、あなたの貴重なご意見がNILTOに反映されるチャンスです。
このタイミングでぜひご利用ください。